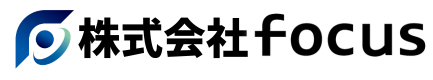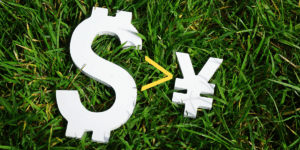vol.5「金利の正体」

日経平均が34年ぶりに最高値更新で、日本の景気が回復しつつあると期待を込めたニュースが連日流れています。しかし、これはチャイナバブルの崩壊で中国市場から投資マネーが一時的に日本に流れ込んでいるに過ぎず、日本の実体経済とは大きく乖離しているように思います。海外からの投資マネーは、他に良い投資先が見つかればいずれ流出していくでしょう。
日本経済の黄金期は1955年ころから始まったと言われます。神武景気、岩戸景気、オリンピック景気、いざなぎ景気と15年もの長きに渡り好景気が続き、その間池田内閣は国民の所得を2倍に増やす「所得倍増計画」を実現。1970年以降は石油危機や物価高騰などで苦しんだものの1990年までは経済成長安定期が続きます。
私自身1964年、第1回東京オリンピックの年に生まれましたが、当時はインフラ整備も十分でなく高速道路、新幹線などの公共事業など日本には山のように仕事があり、人口も増加して日本経済は上昇の一途でした。
経済とは、簡単に言うと物を作り(生産)物を買う(消費)ことです。
売り上げが増えれば経済は成長し、その成長が金利を生み出します。なぜなら、景気が良ければ消費者の購買意欲が増し、物が売れれば、企業はより多くの物を生産するために設備に投資します。資金調達にお金を借りたいと思う企業が増えると、当然金利は上昇します。
反対に、不景気とともに個人消費が減退すれば、企業は物の生産を控え、資金需要が低下し金利は下がります。平常時には1泊5千円のホテルがピーク期には一気に3万円になるのと同じ理屈です。このように金利は経済の成長から生まれてくるのです。それゆえに成長しきった国は金利を失っていく。これは仕方のないことなのです。
実際に経済成長期の1980年代郵便局定期の金利は約12%でした。現在の金利はというと、皆さんご存じの通りです。2020年に中国も黄金期の終焉を迎え、これからはインド、アフリカに黄金期がくるだろうと言われています。人間が成長して老いていくように、国も成長して衰退していく。しかし、世界中のどこかで必ず成長している国があり産業があります。成長が止まった国は、未来の成長国に目を向けることも必要でしょう。

地主の参謀ニュースレター「回帰」2025年4月号掲載